6月18日…自選エッセイ集より【20】
 私は新宿で生まれてから、渋谷に住み着く間に、神奈川県の稲田堤という多摩川の畔に居たことがある。幼稚園と小学一、二年までの数年間なのだが、その頃の記憶が近頃は妙に蘇る。
私は新宿で生まれてから、渋谷に住み着く間に、神奈川県の稲田堤という多摩川の畔に居たことがある。幼稚園と小学一、二年までの数年間なのだが、その頃の記憶が近頃は妙に蘇る。
長らく、他人の人生を眺めているような気持ちになる期間だった。旅先へ向かう家族全員が乗るルノーが、二台の大型トラックに挟まれるという、第一回目の大事故で頭を強く打ったからなのか、あるいは、子供心には余る体験を、記憶から抹殺しようとしたときに、その周りの思い出も巻き添えになったからだと思う。
その人生の中でポッカリ空いた隙間が、一年前、親父を亡くしたことをきっかけに徐々に埋まっていくように感じている。 自分の心の内など、すっかりお見通しのつもりでいたから、これは意外だった。真にトラウマというのは厄介だ。それ以上の何かが起こらない限り、それがあったことさえ気付きもしない。
人生の時間と空間というものは、歳を取る度に加速して狭まるものだから、現在の一年より子供の頃の一年のほうが,遙かに長く、広い。大人になってから記憶を頼りに思い出の場所へ行くと、全てが小さく見えるのもそのためだ。道路の幅。校庭。樹木や塀。そして人も。かつては、チューリップでさえ腰の高さまであり、時間の進行は、もどかしいほど緩やかだった。子供は、僅かの時間に何度も笑い、何度も泣くことができた。 その膨大な思い出が、現在の大人の私に雪崩れ込んできて戸惑うばかりだ。
梨園に囲まれた我が家の、一本の登れば折れる柿の木。畑の赤紫色のレンゲの群生。五円で買えるコロッケ屋さん。多摩川に直角に交わる大通りの中央分離帯の延々と続く桜並木などは、まだあるのだろうか。
空いっぱいの桜が舞う中を、誰かが、親父の所へ行こう、と言って、小さな私をバイクの荷台に乗せて飛ばす。突き当たって土手を上ると、大きな多摩川を見渡せるのだ。川を下って、しばらくいくと、面積ばかりが広い段々畑のような中之島の堰堤がある。バイクは、そこに親父が居ないことを知ると今度は上流に向かう。オフロードだから、お尻が痛かったが、それ以上に楽しく気持ちが良かった。将来、私がオートバイに乗る遠因は、ここにあったのかもしれない。
川の中州に独り人影があり、それが親父だった。鮎の季節でもないのに胴長、今で言うウェーダー姿だったから、どんなに遠くてもすぐに判る。他の釣り人は、もっと釣りやすい所にいて、そんな格好をしていない。
時折、長尺の竹竿が掲げられてキラリと魚が光る。そして気配を察するとしか思えないのだが、遠くにいる我々にすぐに気付いて手を振るのだ。
それにしても、私を親父の元へ送ってくれたこの人は誰だったのか、また何で親父はいつも川にいられたのか、聞く機会が無くなってしまった。
記憶の喪失が解けてきて確信したのだが、この時期程、父子一緒にいたことはない。私は、この土地も、川に佇む親父の姿も好きだった。再び、都会に戻るとき、車の後部座席で一生に一度というぐらいに泣き腫らしたものだ。
渋谷には魚のいる川が無く、子供同士の遊びの質がガラリと変わった。このあたりからの記憶は鮮明である。釣りのほうは、海に行くことが多くなった。親父との思い出は、ほとんど釣りの中にしかないのだが、残念なことに、それも十四歳のときに途切れてしまう。第二の大事故が起こったのだ。。
早朝、親父と二人でイナダ釣りに行く途中、大船というところで居眠りタクシーに正面衝突されて、そのまま仲良く入院することになったのだ。
今初めて思うのだが、親父の身になってみると、自分の運転する車の助手席で、シートベルト無しで二度までも血だらけでボロボロの息子を見ているわけである。尋常な気持ちではいられなかっただろう。 私はと言えば、顔面はガラスでメチャメチャになるし、一時的に目も見えず、前歯も何処かに飛んでしまった。後日聞いたところでは、まるで破裂したスイカのようだったという。
将来の不安など全く無い時に、この体験は重かった。見舞いに来る人が私の顔を見て、卒倒しかけるのだから堪らない。
幸い、失明することもなく、優れた医者のおかげで、幾つかの後遺症を残したものの、なんとか復活した。ただ、半年たってもまだ顔からガラスの破片が出てくるのには参った。私は本当は、もう少し整った顔立ちだった?ノダ。
一年が過ぎ、この間に精神面で大きな変化があった。私はそれを受け入れた。
久しぶりに、親父と釣りに行くことになり、二人が選んだのはイナダ釣り。また同じ道を通ることになる。ただし、今度はシートベルトをガッチリ締めた。さすがに事故現場を通るときは緊張したが、二人は顔を見合わせて頷いたものだ。言葉は無かったものの、お互いが何を思っているかは判った。
この日は、先の不運と帳尻を合わせるかように、爆釣だった。二人の満足感といったら、二度と味わえないものであった。そして、何故か、これ以後親父とは一緒に釣りすることが極端に少なくなった。おそらく変わったのは親父ではなく、私のほうである。
あれから三十年というもの、相談事のひとつも持ち掛けたことのない、カワイクナイ息子を、親父は何を想って見ていたのだろう。歳を取ってからは、いつも海の側に居を構え、晩年はお気に入りの熱海で夫婦水入らずで暮らしていた。
死期が近づいていることを知ると、自宅へ帰りたがり、病院関係者を困らせたようだが、薬をボイコットしてまで我をとおした。自宅のベットからなら海が望めるからだ。母の勘で、亡くなる一日前に呼ばれて、しばらく二人きりになれた。夕刻に、一瞬晴れ間が覗いて海が光ると、とても満足そうだった。
その晩、父は、母と添い寝すると、二度と起きることはなかった…。
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
2003年7月に岳洋社さんの「SW」に掲載されたものです。三日前、何で家族が一時期、多摩川の畔に居たのか、初めて母に聞いてみました。(母は私が文章書いてるなんて知らない)新宿で三歳の私が行方不明になったからだという。ボクのために…。花園神社で保護?捕まったそうです。……この第20話をもって、エッセイのアップは、しばらくお休みします。

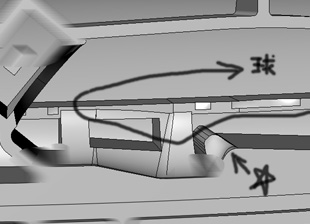







ディスカッション
コメント一覧
こんにちは、Hです。
思い出の場所で4ヒット2キャッチでした。
キャッチしたのは、ヒラフッコですが・・・
ルアーはBKF125カラーは・・・
最初のヒットはST-56伸ばされバラシでした。
その後もフックの伸びた125を使いつづけ3ヒット2キャッチ。
あそこは何故かあの色がいいですね~
これから、お昼寝です。おやすみなさい・・・
Hさん、こんばんは。
私も、今、焼酎飲んでます。
親子対決、増やす……うらやましいナ。でも、親父さんも、さすがに体力が…。
息子の前では、なかなか弱みを見せられないのが、オヤジ達のツライトコロ。そこんとこ、ヨロシク。
日曜日、釣れると良いね。
こんばんは、近所のHです。
お気に入りの焼酎を飲んで酔った勢いで書いています。
自分も幼稚園の頃から親父に付いてまわり、フナ釣り・海釣り・ブラックバス・現在のシーバスと色々な釣りをしてきました。
最近は親父との釣行もめっきり減りましたが、先日の親子ウェーディング対決?のような釣行も、この先何回あることか・・・
70近くなっても、まだまだ元気な親父ですが最近は磯場のシーバスもめっきりです。
これからは、親子対決の回数を増やしたいと思います。
親父のためでは無く自分のために。
※日曜日に思い出の場所に釣行してきます。